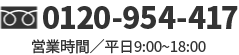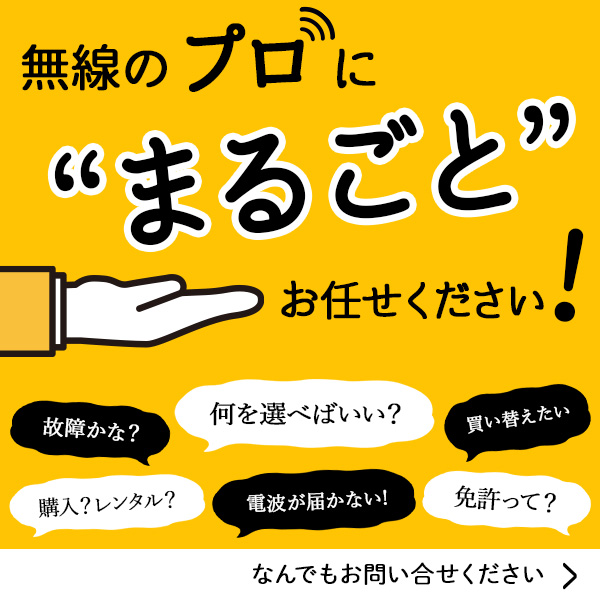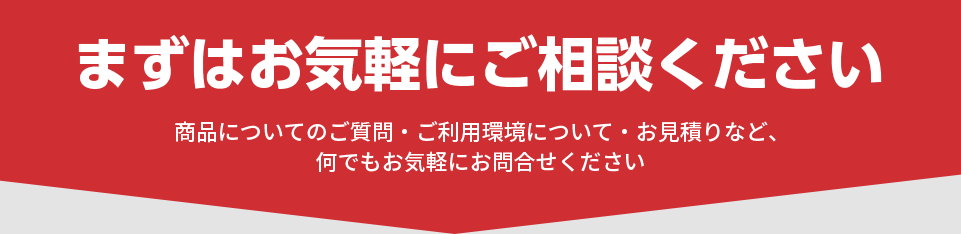DXの代表的な事例5選!DXが必要な理由と推進する際のポイントについても解説
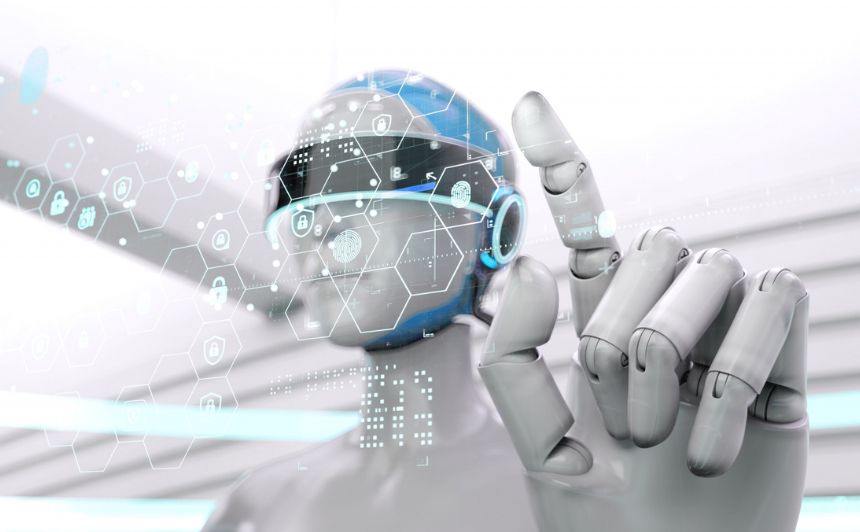
2018年に経済産業省が公表し、現在では企業の重要な経営テーマとして認知されている「DX」ですが、他の先進国と比べると日本のDX化は遅れています。しかし、企業が生産力やブランド力を保ち、今後も存続していくためにはDXの推進が必要不可欠です。
今回はDXの事例を紹介するとともに、DXが必要な理由や推進する際のポイントについて解説します。
DXの代表的な事例5選
DXの事例として次の5社を紹介します。
- クボタ
- セブン&アイ・ホールディングス
- ソニー損害保険
- ユニクロ
- 味の素
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.クボタ
海外に多数の販売子会社を設立し、グローバル展開しているクボタでは、修理対応といったサポートの範囲が担当者のスキル・経験に依存するという課題がありました。この課題を解決するために開発され、販売代理店のサービスエンジニア向けに提供されたのが、3Dモデル・ARを用いた故障診断アプリ「Kubota Diagnostics」です。
このアプリの導入によって、機械故障時のダウンタイム軽減と顧客のコスト削減に成功しました。
2.セブン&アイ・ホールディングス
セブン&アイ・ホールディングスは、グループDXソリューション本部とグループDX推進本部の2体制で、グループ全体のDXを推進している企業です。同社では「攻めのDX」と「守りのDX」の2つのDXを推進しています。
「攻めのDX」では顧客価値の創造・拡大を目指しています。主軸となる取り組みが「ラストワンマイルDXプラットフォーム」です。
「ラストワンマイルDXプラットフォーム」はAIを活用して配送を最適化する取り組みで、拡大する宅配ニーズに対応し、顧客の利便性工場と社会的課題の解決を目指しています。
「守りのDX」は各種セキュリティ対策の実施と、高いセキュリティレベルを誇る共通基盤の構築を目指しています。これらを実現するために、本部にセキュリティ専門人材を集中させ、本部からグループ各社にアドバイスする体制を整備しているそうです。
3.ソニー損害保険
ソニー損害保険では、自動車保険において運転傾向や運転スキルが把握できず、事故リスクが算出できないといった課題がありました。この課題を解決するために開発・提供されたのがAIを活用したスマホアプリ「GOOD DRIVE」です。
このアプリはスマホの各センサーを利用することで、アプリ経由で運転中のデータを収集・分析し、同社が保有する過去の事故データと組み合わせて、事故リスクを算出できます。これにより、安全運転であると判断した運転手に対して、保険料のキャッシュバックを行う「運転特性連動型自動車保険」を提供できるようになりました。
また、事故リスクの可視化によって、運転者自身も運転を見返すことができるため、実際の事故リスクの軽減に寄与できます。
4.ユニクロ
ユニクロを展開しているファーストリテイリングでは、製造小売業から情報製造小売業へと変革するためのプロジェクトを推進しています。同社が目指しているのは「作ったものを販売するのではなく、消費者が求めているものを作る」です。
そのため、実店舗とEコマースの融合や無人レジの導入といったDXを推し進め、顧客視点での業務改革を行っています。また、新しいビジネスモデル構築を実現するために、部署の垣根を超えるよう努めており、デジタル時代に相応しい企業文化に変革しつつあるようです。
5.味の素
味の素グループは、経営基本方針「ASV」を掲げ、目的としている社会変革を実現するためにDXを推進しています。代表的な事例として上げられるのが、包装工程管理システムの開発・導入によるスマートファクトリー化です。
記録媒体を紙からアプリへと変更し、稼働データの自動記録を実現することで、リモートによる現場管理やスピーディなデータ分析、管理業務の標準化に成功しました。また、教育・採用面ではDX人財増強計画を策定し、人員増強数を重点KPIに設定しています。
そもそもDXとは?
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは、企業がAIやビッグデータといったデジタル技術を活用して、新しいビジネスモデルの創出や業務効率化だけでなく、企業風土の変革や旧システムからの脱却を目指す取り組みのことです。
日本では2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」を契機に認知度が広がり、現在では企業が競争優位性を維持し続けるための重要な経営テーマとなっています。
デジタル化との違い
デジタル化とは、紙で管理していたものを電子化するというように、既存のシステムをデジタル技術に切り替えて、業務効率化を図ることです。DX化とデジタル化の違いは、その目的です。
デジタル化はデジタル技術に切り替えれば、目的が達成されます。一方、DX化は業務をデジタル化した上で、企業の変革や利益につながる取り組みを継続しなければ達成されません。
つまり、デジタル化は「DX化のスタート」地点であり、共通する部分はあるものの、同じ意味ではないということです。したがって、両者を混同するのは避けた方がよいでしょう。
DXを推進できている状況とは?
2021年9月に発表された「IMD世界デジタル競争力ランキング2021」によれば、日本は64ヶ国中28位と他の先進国と比較するとDX化が遅れています。DX化が遅れている要因は様々ありますが、業務のデジタル化をDX化だと勘違いしていることも要因の1つだといわれています。
前述のとおり、デジタル化は「DX化のスタート地点」であり、業務をデジタル化するだけでは、DX化したとはいえません。デジタル技術の特性を生かしながら、企業の変革や利益につながる取り組みを継続してはじめてDXを推進しているといえます。
ただ、DX推進と一口にいっても、取り組み方は様々です。そのため、DXを推進できている状況とはどのようなものなのか、分からないという方は多いでしょう。
DX推進ガイドラインを参考にすると、DXを推進できている条件は次の3つだと解釈できるでしょう。
- 環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる状態である
- 新しい価値創造に向けて構築すべき経営ビジョン・ビジネスモデルを示している
- 事業を変革できる企業体制が整備されている
DXが必要な3つの理由
DXが必要な理由として次の3つが挙げられます。
- 少子高齢化による労働人口の減少
- ユーザーの行動形態の変化
- 既存モデルの抜本的な改革
それぞれ詳しくみていきましょう。
1. 少子高齢化による労働人口の減少
少子高齢化によって労働人口の減少が加速しています。総務省が公表している「平成29年版 情報白書」では、2025年の15歳~64歳人口は約7,058万人ですが、2035年には約6,343万人、2045年には約5,353万人になると予想しています。
ただ、日本の出生数は急減しており、2022年の出生数は80万人を割りました。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)では、出生数の80万人割れは2030年と推計していたことから、大幅に早まっており、労働人口も推計より早く減少することが予想されます。
労働人口が減少すれば、企業は人手不足が慢性化し、現状の生産力を維持するのが困難となります。少ない人数でも生産力を維持・向上させるためには、業務効率化や既存のビジネスモデルを変革するDXを推進しなければなりません。
2.ユーザーの行動形態の変化
ユーザーの行動形態が変化したこともDXが必要な理由の1つです。スマホの普及によって、現代ではインターネットの利用が日常化しました。
その結果、オンラインで商品を購入したり、SNSで情報収集したりするなど、ユーザーの行動形態は大きく変化しています。また、新型コロナウイルスが流行した2020年以降は多くの企業がECサイト分野に参入したことで、ネットショップは今まで以上に乱立し、競争幅も大きく拡大しています。
ユーザーの行動形態の変化に対応し、競合他社との差別化を図っていくためには、DX推進が欠かせません。
3.既存モデルの抜本的な改革
業務を効率化するためにデジタル化を進める企業は多いですが、デジタル化によって商品・サービスがコモディティ化しています。コモディティ化とは、市場参入時に価値が高かった商品・サービスが市場活性化によって市場価値が低下し、一般的な商品・サービスになることです。
コモディティ化してしまうと、ブランド力や機能などの差別価値が薄れてしまうため、自社ブランドを保つことができません。自社ブランドを保って企業を存続させるためには、デジタル時代に相応しい企業文化に変革させて、既存モデルの抜本的な改革を行う必要があります。
DXを推進するメリット
DXを推進するメリットとして次の3つが挙げられます。
- 働き方改革につながる
- 業務を効率化できる
- 新規ビジネスを生み出せる
DXを推進すれば、業務効率化や働き方改革にも寄与できるため、従業員満足度の向上や離職率の低下が見込めます。また、新規ビジネスを生み出すことができ、利益の拡大も期待できるでしょう。
DXを推進するデメリット
DXを推進する際のデメリットとして次の3つが挙げられます。
- 会社全体で取り組む必要がある
- DX実現まで時間がかかる
- 改修時の作業が大規模
DXを推進・実現するためには、これらのデメリットをしっかりと理解しておかなければなりません。
DX推進の具体的なステップ
DX推進の具体的なステップは次のとおりです。
- DX推進する目的の明確化
- 責任者の許可を得る
- 企業・業務などの現状把握および課題点の洗い出し
- 課題点・現状を加味しながらDX戦略を策定
- 実施していく優先順位をつける
- 優先順位に沿って業務をデジタル化
- 企業全体のワークフローをデジタル化
- 事業のビジネスモデルを変革
- 定期的にPDCAを回す
目的が明確になっていないと、取り組みが中途半端になったり、失敗を招いたりします。そのため、なぜDX推進するのか目的を明確にしたうえで取り組むことが大切です。
DXを推進する際の4つのポイント
DXを推進する際のポイントとして次の4つが挙げられます。
- DX人材の確保・育成
- トップが積極的に携わる
- レガシーシステムからの脱却
- スモールスタートではじめる
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.DX人材の確保・育成
企業がDXを推進していくためには、DXを扱えるIT人材の確保が欠かせません。しかし、DX推進が企業の重要なテーマとなる中で、IT人材需要は拡大しています。
そのため、IT人材は不足しつつあり、経済産業省が平成31年に公表した「IT人材需給に関する調査(概要)」によれば、2030年には低位シナリオでも約16万人、高位シナリオでは約79万人不足するといわれています。
今後、円滑にDX推進を確保していくためには、DX人材の雇用だけでなく、他社と協業しながら、自社内でDX人材を育成していく必要もあるでしょう。
2.トップが積極的に携わる
DXは業務の1部を電子化するデジタル化とは違い、風土・文化など、企業全体を大きく変革していく取り組みです。
そのため、DXを成功に導くためには、担当者にすべてを任せるのではなく、企業のトップが積極的にDX推進に携わっていく必要があります。
3.レガシーシステムからの脱却
「レガシーシステム」とは、過去の仕組み・技術で構築されたシステムのことです。1980年代に多くの企業が導入したオフコンやメインフレームを使用したシステムのことを指します。
古いシステムであるがゆえに、レガシーシステムを扱える技術者は高齢化し、少なくなってきています。また、サポートが終了していたり、カスタマイズできる社員がいなくなったりしてシステムが形骸化していることも少なくありません。
これらのシステムは保持しているだけでもコストがかかりますし、情報漏えいのリスクもあります。そのため、DX推進の過程でシステムを刷新し、レガシーシステムからの脱却を図らなければなりません。
4.スモールスタートではじめる
「スモールスタート」とは、業務の1部から小さくはじめ、運用状況を鑑みながら徐々に適用範囲を拡大していくことです。DXは企業全体を大きく変革していく取り組みであるため、いきなりすべてを変えてしまうと、現場が混乱して問題が頻発し、DX化に失敗するリスクが高まります。
そのため、業務の1部やツールを導入する部署を絞るなど、まずは小さくはじめ、効果検証を行いながら、徐々に範囲を拡大して企業全体のDX化を進めていくことをおすすめします。
まとめ
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは、デジタル技術を活用して、企業風土の変革やレガシーシステムからの脱却を図る取り組みのことです。少子高齢化やユーザーの行動形態の変化などによって、企業経営は大きな転換期を迎えています。
現行の経営方法では、企業の競争優位性は失われ、存続し続けることはできません。現状の生産力や自社ブランドを保ち生き残っていくためにも、DXを推進してデジタル時代に相応しい企業文化・体制に変革させていきましょう。